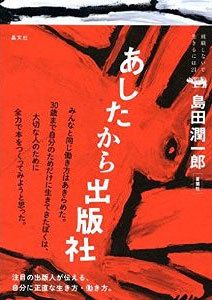「中上のことは昔から知っているんだ」
翌朝、ホテルを出て、ぼくは新宮の町の本屋さんへと歩いた。荒尾成文堂という、老舗の本屋さんである。ここはネットで検索して、見つけた。学生時代、中上健次の『枯木灘』に衝撃を受け、和歌山の本屋さんを取材するなら、中上と関係する本屋さんを取材したいと決めていたのである。
それにしても、新宮は不思議なところである。見渡すと、町が山々に囲まれていることがすぐにわかる。土地はせまい。海辺の町といった雰囲気はまったくないのに、東側は海に面している。通りは静かで、陽光は強い。ぼくの知る限り、どの町にも似ていない。それなのに、強烈な既視感がある。郷愁がある。
荒尾成文堂に入ったときも、どういうわけか、なつかしいような気持ちになった。陽射しが強い日だったので、店のなかは、最初、暗く見えた。真ん中に小さなレジがあって、そこを境に、文房具売り場と、書籍売り場とに分かれていた。
「はじめまして。夏葉社の島田です」と帳場にいた店主の荒尾さんに声をかけると、「おお、来たのか」と大きな声がかえってきた。本当は「おお、来たんか」と強いなまりで言ったと思うのだけれど、方言やなまりをうまく再現できないので、ここでは標準語で記す。
すぐに、店の入り口近くの中上健次コーナーに気づいた。棚一本がまるまる中上関連の本でうまっていた。入り口のドアのうえには、中上の写真がたくさん飾ってあった。熊野にかんする郷土本も山のようにあった。
「すごいですね」と言ったら、「すごいだろ」と言って、さっそく中上の本をいくつか持ってきてくれた。最近だと『本の雑誌』に中上の特集が載ったのだと言って、その特集が載ったページを開けて、ぼくに見せてくれた。
荒尾さんは「中上のことは昔から知ってるんだ」と言った。
ぼくはそのことすら知らなかったので、「そうなんですか?」と驚いて、次から次へと、この偉大な作家のことについて話を聞いた。
荒尾さんは、中上健次より、ふたつ年上である。高校が同じで、中上は体が大きかったから、高校でも目立つ存在だった。そのころは、荒尾成文堂は、荒尾さんのお父さんが運営していて、中上は文芸書が揃うこの店へよくやってきていた。そして、『週刊読書人』や『図書新聞』を買っていった。どちらも、普通の高校生であればまず読まないような、本格的な書評専門紙である。「ほかの店では売ってないんだ」と10代の中上は言った。そして、「今は金がないから、ツケにしといてくれ」と言い足した。
ぼくは頭がぽーっとなった。
雑誌の発売日になると、待ちこがれたように本屋さんに入ってくる。雑誌を買ってすぐ店を出ることもあれば、店内にしばらくとどまるときもある。30坪の店に並ぶ本を真剣なまなざしで眺め、1冊の本をためつすがめつ眺める。子どものころから、きっと、そうなのだ。とりつかれたように、町の本屋さんへ通ったのだ。
荒尾さんは、晩年まで、作家とつきあった。やさしい男だったと言った。
ぼくは荒尾成文堂をあとにすると、中上健次のお墓を訪ねるために、駅前で自転車を借りた。
中上の墓は、坂の上にあった。
ぼくは痔の痛みに耐えながら、一所懸命、ペダルを漕いだ。
●次回予告
日本国内をくまなく歩いてつくられた『本屋図鑑』。だが、島田さんの本屋めぐりは国内だけには留まらない。どの国のどの町を歩いていても、気がつくと本屋を探している。その彷徨が積み重なると『本屋図鑑』が生まれるのかもしれない。次回《「アフリカの本屋さん》。8月4日(日)公開予定。